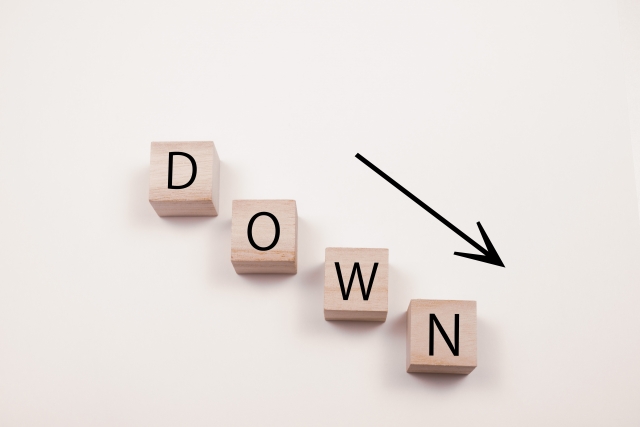いぼ痔(内痔核・外痔核)は、直腸肛門部の血管が腫れて盛り上がることで発症し、初期には排便時のわずかな違和感や軽いかゆみ程度で済むことも少なくありません。しかし、放置したり自己流の対処で誤魔化していると、症状は徐々に進行し、日常生活に支障を来す深刻なトラブルへと発展します。
悪化したいぼ痔では、痛みや出血が明確に増し、排便はもちろん歩行や座位でも不快感を伴うようになります。さらに症状が進行すると、血栓が形成されて激しい痛みを引き起こす「血栓性痔核」や、感染から潰瘍を生じるリスクが高まり、全身への悪影響も無視できません。特に高齢者や貧血傾向にある方では、慢性的な出血によって貧血症状が現れ、倦怠感や集中力低下を招くこともあります。
本記事では、いぼ痔が悪化した場合にどのような症状・合併症が生じるのかを明らかにし、早期に手を打つための指針を示します。
いぼ痔の進行状況
第Ⅰ度~第Ⅳ度
いぼ痔は進行度に応じてⅠ度からⅣ度まで4段階に分類されます。Ⅰ度は痔核(血管のふくらみ)が直腸内にとどまり、排便時に軽い出血や違和感を覚える程度です。Ⅱ度になると排便時に痔核が肛門外に脱出し、自然に戻るようになります。Ⅲ度では脱出した痔核を手で押し込まないと戻らず、つねに不快感や痛みを伴うことがあります。最も重いⅣ度では痔核が常時肛門外に飛び出し、指で戻すことも困難になり、血行障害や感染リスクが格段に高まります。
痛み・かゆみ
Ⅰ度では「チクチク」「ムズムズ」とした刺激が中心ですが、Ⅱ度以降は排便時の引っかかり感や突き上げるような痛みが現れます。特に便が硬い場合や下痢で刺激が強まると、裂傷や炎症が重なり、ズキズキと激しく痛むこともあります。Ⅲ度・Ⅳ度に進行すると、座っているだけで痛みが続き、夜間や歩行時にもかゆみと鈍痛が慢性的に続くため、睡眠障害や集中力低下を招くことがあります。
出血量の増加
初期はトイレットペーパーに鮮紅色の点や線がわずかに残る程度ですが、進行につれて便器にポタポタ落ちるほど出血が増えます。Ⅱ度以上では排便直後に鮮血が流れ落ちることがあり、Ⅲ~Ⅳ度では安静時でもじんわり血がにじむケースも珍しくありません。大量出血が続くと貧血を引き起こし、めまいや動悸、倦怠感を伴うため、放置せず医療機関を受診する目安となります。
悪化によって起こる合併症
血栓性痔核
いぼ痔が長期間炎症を起こして血流が滞ると、痔核内部に血栓ができやすくなります。これを血栓性痔核と呼び、急激に固く腫れ上がることで激しい刺すような痛みを引き起こします。痛みは通常の痔痛よりも強烈で、排便だけでなく安静時でも続くため、早急な医療的処置が必要になることがあります。
感染・潰瘍形成
痔核周囲の皮膚や粘膜が傷つくと、細菌が侵入して感染を起こす恐れがあります。炎症が慢性化すると皮膚がただれて潰瘍状になり、排便や歩行時に強い痛みを伴うほか、膿や悪臭を伴う分泌物が出る場合もあります。こうした状態を放置すると、さらに深部の組織まで炎症が広がり、より侵襲的な外科的治療を要するケースも少なくありません。
貧血や全身倦怠感
慢性的な出血が続くと、徐々に鉄分や血液量が不足して貧血を引き起こします。貧血症状としては、めまい、動悸、肌の青白さ、疲労感や集中力低下などが現れ、日常生活に支障を来すことがあります。特に高齢者やもともと貧血傾向にある方は症状が顕著になりやすいため、出血のサインを感じたら早めに検査を受けることが重要です。
日常生活への影響
仕事や外出時
いぼ痔が悪化すると、座位や立位を続けるだけでも肛門部に鈍い圧迫感や痛みを感じるようになります。長時間のデスクワークでは、椅子の硬さが痛みを助長し、つい姿勢を変えたり立ち上がったりを繰り返すため集中力が低下しがちです。また、外出先のトイレでは座浴や体勢の調整が難しく、排便のたびに痛みに耐えねばならず、外出そのものを億劫に感じるケースも少なくありません。こうしたストレスの蓄積は、仕事のパフォーマンスの低下だけでなく、精神的にも疲弊を招くため、早めに対策を講じることが重要です。
さらなる悪化
排便のたびに痛みや出血を避けようとしてトイレでの時間を短縮したり、無理に便を我慢したりすると、肛門周囲の血行不良が進行し、痔核がさらに腫大するリスクが高まります。特に、硬便を無理に排出しようといきむ行為は、肛門内の血管に過大な圧力をかけ、痔核を悪化させる大きな要因です。トイレでの姿勢を正し、足台などで膝を高くすることで排便をスムーズにし、慌てずにゆったりとした呼吸でいきみをコントロールするセルフケアを心がけましょう。加えて、排便後にはぬるめの座浴で肛門周囲を清潔に保ち、温めることで血流を改善し、炎症を抑える工夫が有効です。
いぼ痔の悪化を防ぐケア
生活習慣の見直し
食生活の改善は、いぼ痔の悪化予防において最も基本的なポイントです。食物繊維を豊富に含む野菜や海藻、豆類を積極的に摂ることで便のかさが増し、排便がスムーズになります。特に朝食におくらや切干大根などの水溶性・不溶性繊維を組み合わせると、腸内環境のバランスが整い、硬便や便秘を防ぎやすくなります。また、排便習慣を一定に保つためには、毎日同じ時間帯にトイレに座り、無理にいきまないことが重要です。食後に便意を感じることが多いので、朝食後の15~20分を目安にトイレの時間を設けると、習慣化しやすくなります。
入浴・トイレ
肛門周辺を清潔かつ温かく保つことは、血行を促進し炎症を抑えるうえで効果的です。入浴時はシャワーだけで済ませず、ぬるめ(38~40℃程度)のお湯に10分程度ゆったりと浸かることで、肛門部の緊張がほぐれ、血流が改善します。座浴用のバケツやビニール製洗面器を活用すれば、仕事帰りの手軽なセルフケアとしても続けやすいでしょう。トイレ環境では、足元に小さな台(踏み台)を置き、膝をわずかに高くすることで直腸と肛門の角度が浅くなり、いきむ力が分散されて排便がスムーズになります。これにより肛門周辺への負担が軽減し、痔核への圧迫を緩和できます。
市販薬や座浴
症状が軽いうちは、市販の坐剤や軟膏を適切に使うことで炎症を抑え、悪化を防ぐことが可能です。軟膏は外用部位に薄くのばし、坐剤はできるだけ排便後すぐに挿入すると効果が高まります。ただし、長期間の連用は肌の乾燥や薬剤耐性のリスクがあるため、1回あたりの使用量や使用期間は添付文書を守りましょう。座浴に用いる入浴剤(消炎・抗菌成分配合のもの)を選ぶと、効率的に炎症を抑制できます。市販薬だけで改善が見られない場合は、自己判断で使用を中止せず、速やかに専門医に相談することが大切です。
治療法の選択
坐剤・軟膏
軽度から中等度のいぼ痔に対しては、まず薬物療法が第一選択となります。坐剤は直腸内の痔核周辺に直接薬剤を届け、炎症を抑えながら血流を改善します。軟膏は外痔核や肛門周囲のかゆみ、痛みを和らげる効果があり、患部に薄く塗布するだけで局所の症状緩和が期待できます。外来で処方される薬には、血管収縮作用を持つ成分や抗炎症成分、痔核のうっ血を軽減する成分が配合されています。一般的に数週間の使用で改善が見られない場合は、次の処置を検討します。
低侵襲処置
薬物療法で十分な改善が得られない場合、より積極的に痔核そのものにアプローチする処置が行われます。硬化療法は、痔核内部に硬化剤を注入し、血管を閉塞させて痔核を縮小させる方法です。処置自体は数分で終わり、日帰りで受けられることがほとんどです。結紮術(ゴムリング療法)は、痔核の根元に小さなゴムリングを装着し血流を遮断して自然脱落を促す治療で、比較的痛みが少なく回復も早いのが特徴です。どちらも局所麻酔下で行われ、入院は不要ですが、数日間の出血や違和感が続く場合がありますので、処置後の安静と医師の指示に従った経過観察が重要です。
手術
Ⅲ度・Ⅳ度の重度痔核や、硬化療法・結紮術でも再発を繰り返す場合は、外科的切除術が検討されます。伝統的な痔核切除術(ミリガム法やファーラー法)は、痔核を切除し縫合する確実性の高い手術ですが、術後の疼痛や排便時の違和感が数週間続くことがあります。一方、PPH法(Procedure for Prolapse and Hemorrhoids)やDST吻合器を用いた手術は、切除範囲を最小限に抑えて痔核の粘膜を上方に引き上げるため、術後痛や出血が少なく回復が早いのが特長です。手術法の選択は痔核の状態や全身状態、患者の希望を総合的に判断して行われるため、専門医との十分な相談と術前検査が欠かせません。
まとめ
悪化したいぼ痔は痛みや出血のみならず、日常生活全般に大きな負担をもたらします。しかし、適切なセルフケアと早めの医療介入によって、多くの場合は症状の進行を食い止め、快適な生活を取り戻すことが可能です。まずは便通を整える食事習慣や排便姿勢の工夫、入浴・座浴による血行促進を日々のルーチンに組み込みましょう。市販の坐剤・軟膏も用法を守って活用し、炎症や痛みの軽減に役立ててください。
もし数週間のセルフケアで改善が見られない場合や、強い痛み・大量出血を感じたときは、躊躇せず専門医を受診することが不可欠です。薬物療法や硬化療法、結紮術といった低侵襲処置、重症例には切除術やPPH法など、症状やライフスタイルに応じた最適な治療法が選択されます。早期に適切な治療を受けることで、合併症リスクを抑えつつ再発の可能性も低減できます。